藤間秋男のブログ
2020.12.10 Thu
東京商工リサーチの調べによると、2020年の1~9月の「後継者難」による倒産が278件あります。これは前年同期比で1.5倍以上増加しています。中小企業の事業継承が難しくなっているという現状が数字からも伺えます。こういった現状を踏まえて藤間の考える問題点とその解決法をお伝えします。
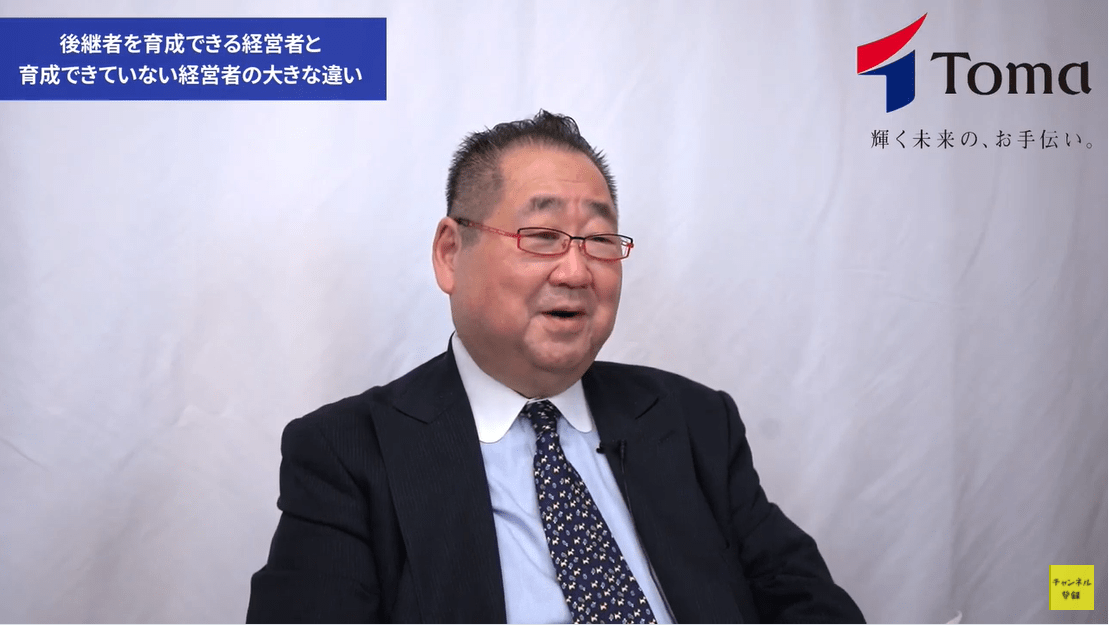
「後継者難」とよく言われますが、常に後継者をつくる努力をしていないんですね。現状の中小企業の社長の平均年齢は65歳くらいと言われています。若い社長もいらっしゃいますが、一番多い年齢は68,69歳です。
68,69歳になった社長たちは後継者をつくっていないわけです。後継者をつくっていない社長というのは死生観がないんですね。要するに自分は永遠に生きていると思っているわけです。150歳ぐらいまで生きるという感覚の人が非常に多いです。
そのため、後継者をつくりません。後継者をつくらないと会社が残らないんですね。企業創りのために、90歳になっても社長をやれますかといっても、その歳では社長は出来ないです。

特に今はテレワークやIT化など、どんどん世の中が変わっています。雇用する社員の意識や、お客様の意識も変わっている中で、80、90歳で社長をやっていたら世の中に必ず乗り遅れて潰れます。
後継者難というのを倒産というのですが、要するに後継者を作らない社長の会社は倒産予備軍だということです。
そして、後継者をつくっていない社長というのは一事が万事です。
後継者をつくらないといけないということが1つあるとして、市場を開拓しないといけない、新商品を開発しないといけないなど、そのほか色々な事をやらないといけないのに、出来ていない社長が多いということが、言えると思います。
ある意味、子どもがいるところはその子どもが継ぐというのが自然でしょうね。ところが、子どもが継がない例も多くあります。
私の会社もそうですが、父親の姿を見て自分は同じように出来ないとか、父親が子どもに仕事に対してあまり良い印象を持たせなかったりしていると、子どもが後を継いでくれません。

私の仲間の子供が「パパの仕事は継がない」と言ったそうなんです。その話を周りに話したら、「家ではどんな話をしているの?」と聞かれて、考えてみたそうです。
外では愛想よくしているけれど、家ではぶすっとして、会社の悪口は言うけれど、それ以外会社の話をしていなかったそうです。
彼はある日から家に帰ると「パパの会社はいい会社だよ。今日はこんな良いことがあったよ」と仕事の話をし出したそうです。そうしたら、小学校の卒業文集に「パパの仕事を継ぐ」と書いていたそうなんです。
やはり、こういう努力を日頃からしていかないといけないですね。

子どもに継がせないのであれば、社員に継がせることを考えていろんな仕組みをやる必要があります。
私たちにはその点に関してはすごくノウハウがあります。私にご質問いただけたら後継者づくりの相談にのることが出来ます。会社を社員に継がせることも出来ますし、一代飛ばして孫に継がせるという方法もあり、実際にそう考えている人もいます。

きちんと後継者に継ぐことをしていかないといけません。
仕事には「緊急な仕事」と「緊急ではない仕事」がありますが、後継者をつくるというのは後者の「緊急ではない仕事」なります。そして、「緊急ではない仕事」かつ「重要な仕事」になります。
今年はコロナのこともあり、目先の売上などに目が行きがちになっていますが、「緊急ではないけれど、重要な仕事」として後継者づくりに取り組む必要があります。
目先のことに目が行きがちですが、何十年も後回しにしてしまう会社が多いです。それを我々はコンサルタントとして「後継者を探しましょう、つくりましょう、教育しましょう」ということを指導させていただいています。
放っておくとなかなか取り掛かれない後継者問題について、共に考えて取り組んでいただくことで、後継者を探したり、つくったり、育てたりすることが私たち後継者問題に関するプロの役割だと思っています。
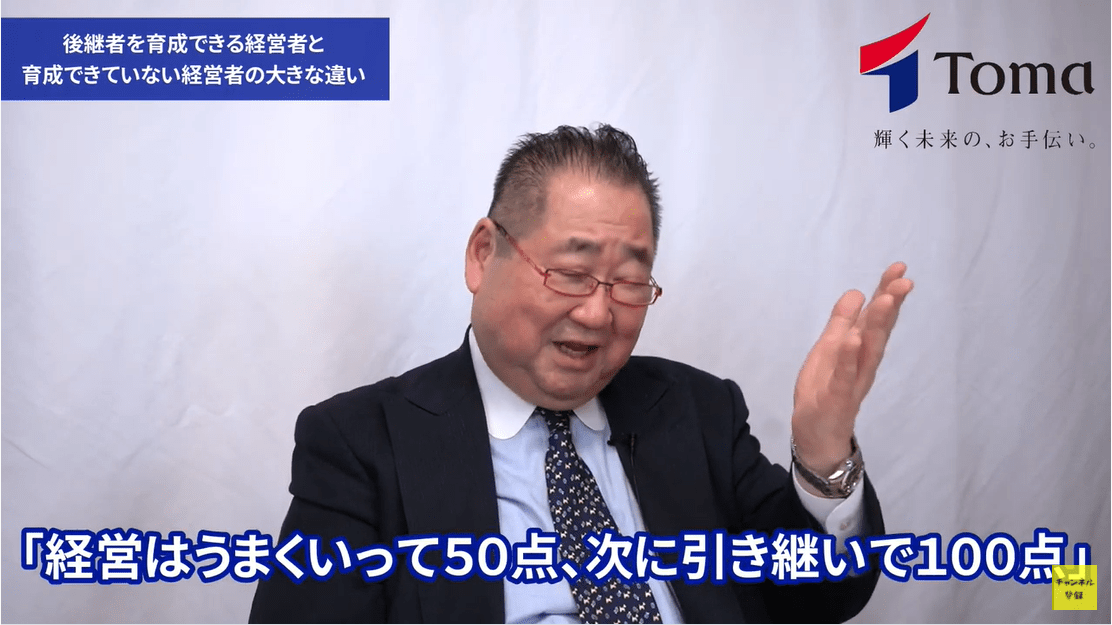
一番重要なのは、「事業継承の経営計画」を立てることです。いつ、どうやって後継者をつくり、託していくのかを10年くらいかけてつくっていかなければなりません。これが出来ないと後回しになってしまいます。
本田味噌本店の社長から後継者に関していい言葉を聞きました。
「経営はうまくいって50点、次に引き継いで100点」
経営は上手くいったとして、それでは50点。後継者にちゃんと引き継ぐことが出来て100点です。要するに後継者を育てるところまでやらないと、100点にはならないということです。
私の会社(トーマコンサルタンツグループ)は後継者に引き継いで3期目になります。今の社長は非常によくやってくれていると思っています。ですから、70点くらいはもらえるかなと思っています。

「ユニクロ」の柳井さんや「ソフトバンク」の孫さん、「日本電産」の永守さんは社長を譲ったけれども、結局上手くいかずまた社長に戻りました。
彼らの場合は本田味噌本店の社長で例えていうならば、50点ということです。会社の規模を大きくすることはいいですが後継者を育てることに苦労しているのではと思います。なぜかというと、彼らは後継者に経営を任せるという我慢が出来ないのです。
後継者をつくることはかなりの我慢が必要です。
「ジャパネットたかた」の創業者はパッと辞めました。取締役などとして、会社に残らずに、きっぱり辞めました。そして、後継者は創業者より30%以上の売上をあげています。こういった創業者の姿は本当にすごいなと思いますね。
会社を存続させるには後継者を育てる仕組みを作っていかないと難しいですし、先代が経営に口を出さないようにしないと後継者は育ちませんし、嫌になってしまいます。このあたりが後継者を作る際の難しさです。
100年続く企業にするには後継者にバトンタッチしていかなくてはいけません。
後継者問題について、会社の社長さんや後継者の人にはぜひしっかりと考えていただきたいです。